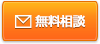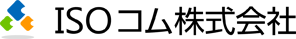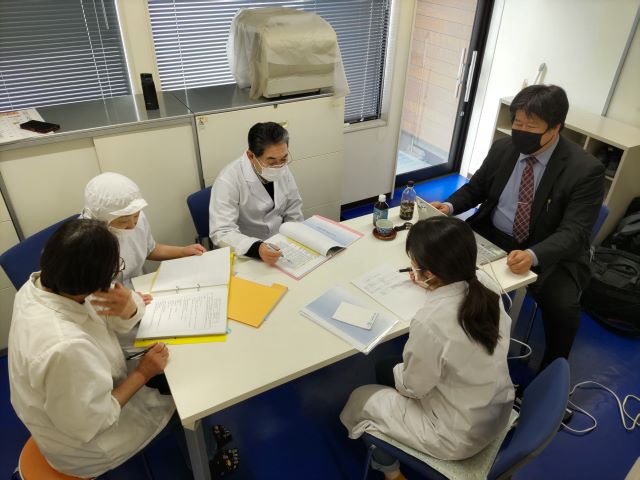JFS-B規格の要求事項ポイント
投稿日:2019年10月15日 最終更新日:2025年3月26日

こんにちは。ISOコム株式会社 芝田 有輝です。
今日のテーマは“JFS-B規格の要求事項ポイント”についてお話ししたいと思います。
Contents
JFS-B規格について
JFS-B規格とは、食品安全マネジメント協会が立ち上げた食品安全規格で、
比較的取り組みやすく、食品衛生法第51条のHACCP制度化に対応しているだけでなく、ISOに比べて取り組みやすく、費用も安いので食品工場様に人気です。
2025年3月7日現在で、2506件の取得件数があります。
ただ、注意すべき点もあるので、今回はその当たりを踏まえてお話ししたいと思います。
JFS-A・JFS-B・JFS-Cの違い
1.主な違い
①JFS-A
基本的な衛生管理(GMP)のみを対象とします。
②JFS-B
JFS-Aの内容に加え、HACCPと食品安全マネジメントシステム(FSM)の導入が求められます。
③JFS-C
JFS-Bに加えて国際基準(GFSI承認)を満たすもので、海外輸出や大規模取引を行う企業向けの厳しい管理が必要になります。
2.GMPの違いと対応事例
①JFS-A
従業員の衛生管理が求められ、例えば手洗いルールを決めて作業前後に徹底することや、作業着を清潔に保つことが重要視されます。
②JFS-B
交差汚染の防止が求められ、生肉を扱うエリアと調理済みエリアを完全に分けることや、まな板や包丁を色分けして食材ごとに使い分けることが必要です。
③JFS-C
さらに高度なアレルゲン管理が求められ、アレルギー特定原材料の取り扱いルールを作成し、記録を残すことが義務化されます。さらに、乳製品と小麦など、アレルゲンを含む食品を扱うエリアを物理的に分離することが求められます。
3.HACCPの違いと対応事例
次に、HACCP(危害分析)の要求事項についてです。
①JFS-A
HACCPの導入は不要です。
②JFS-B
HACCPの導入が義務付けられています。例えば、お弁当工場では、ご飯の炊き上がり後に60℃以上で管理し、調理後は急速冷却して10℃以下にすることで、細菌の増殖を防ぐ対策を行う必要があります。
③JFS-C
さらにモニタリング記録の強化が求められ、温度管理のデータをデジタル記録し、過去の履歴を管理できるようにすることが必要です。また、異常が発生した場合の対策ルール(是正措置)を事前に整備し、万が一の際に迅速な対応ができる仕組みを構築する必要があります。
4.トレーサビリティ(追跡管理)の違いと対応事例
トレーサビリティ(追跡管理)についても違いがあります。
①JFS-B
原材料のトレーサビリティ管理が求められ、使用する野菜や肉の仕入れ先を記録し、原材料の入荷日と使用日を把握できる仕組みを作る必要があります。
②JFS-C
さらにサプライヤー(仕入れ業者)監査が義務化されます。例えば、お弁当工場では、野菜の農薬使用状況を確認する監査を実施し、仕入れ先の工場も監査対象とする必要があります。
JFS-Bが適している企業とは?
JFS-Bは、国内で食品を製造・販売する企業や、HACCPに基づいた管理を導入したい企業、取引先からHACCP対応を求められている企業に適しています。
例えば、コンビニ向けのお弁当工場や、大手スーパー向けの総菜工場などが該当します。
一方で、HACCPを導入しない小規模な食品事業者であればJFS-Aで十分ですし、海外輸出を目指す企業はJFS-Cを取得する必要があります。
JFS-B規格と監査可能な業種分類
JFS-B規格でまず知っておかなければいけないことは何なのでしょうか?
それはJFS‐B規格が対象としているのが、あくまで「食品製造業者」にほぼ限定されているのです。
分類について
セクターといって、食品の種類をCとKの2種類に分け、Cは更に4分類されています。
①CⅠ:腐敗しやすい動物性製品
②CⅡ:腐敗しやすい植物性製品の加工
③CⅢ:腐敗しやすい動物性植物性製品の加工(混合製品)
④CⅣ:常温保存製品の加工
⑤K:化学製品(生化学製品を含む)の製造(食品原料または食品製造の加工助剤として使用される化学製品(生化学製品を含む)および培養物の製造
つまり、一次生産業(農業、漁業、畜産業等)、小売業(仕入れて、そのまま販売)、ケータリング(料理を指定場所に届ける、現地で提供するサービス)業などは、対象外となります。取得を検討する際には監査会社へ事前確認が必要です。
JFS-B規格要求事項のポイントとは?
ここからが本題です。JFS規格は、以下の3部構成でできており、各パートに取組む際の要点があります。
・マネジメントシステム(仕組み)
・HACCP
・GMP(一般衛生管理)
では、主な要求事項を見ていきましょう。
Part 1:FSM(食品安全マネジメントシステム)
FSMは、食品安全の仕組みを構築し、事故防止・再発防止のための改善を行うことが目的です。HACCPを導入する前に、まずFSMの基礎をしっかり整えることが重要です。以下にFSMの主要な箇所を解説します。
① 食品安全方針(FSM2)
経営層(社長、工場長など)が食品安全に関する方針を決定し、それを従業員全体に浸透させることが求められます。
例えば、食品工場では「食品安全を最優先し、安全な製品を提供することを約束する」といった方針を掲げ、朝礼や掲示板で従業員に伝えます。
監査では、現場の従業員が方針を理解し説明できるかを確認されるため、単なる形だけの方針ではなく、実際に従業員が理解して仕事をしているかどうかが重要です。
② 作業手順の可視化(FSM10)
作業手順を明確にし、従業員が必要なときに確認できる状態にすることが求められます。
例えば、食品工場で揚げ物を行う場合、「油の温度は180℃を超えないこと」「調理後はすぐに冷却すること」など、重要な手順を掲示物(イラスト付きが好ましい)として表示することで、ミスを防ぐことができます。
③ 不適合対応と是正(FSM12・FSM13)
不適合(食品の異常やクレーム)の原因を調査し、再発防止策を講じることが必須です。
例えば、お弁当工場で「おかずに異物が混入していた」場合、その原因を調査し、「作業台の清掃頻度を○○回行う」「手袋の破損を定期的○○に一度確認する」といった具体的な対策を実施します。
④ サプライヤー(供給者)の管理(FSM16)
食品の原材料や包装資材をどのように選び、管理するかを定めることが求められます。
例えば、仕入れた材料に異物が含まれていた場合、それが発覚した際の対応策(仕入れ先の変更、品質基準の見直しなど)をあらかじめ決めておく必要があります。
⑤ 食品防御(FSM22)
食品への意図的な攻撃や偽装を防ぐための仕組みを整える必要があります。
例えば、食品工場では「来客が勝手に製造エリアに入らないよう、事前の登録、入退室記録を管理」「出入り口、原材料保管庫、製造ラインに監視カメラを設置、録画データを保存」「製造エリア入室時に従業員の私物チェック」といった対策を実施し、不正な混入を防ぐ必要があります。
⑥ トレーサビリティ(FSM24)
食品安全に関わる事故が発生した際に、影響を受けた製品を迅速に特定し、適切に対応できるようにする必要があります。
例えば、「製造後に出荷した弁当の中に異物(金属片)が混入していると消費者からクレームが発生」となった場合、どの原材料を使用し、どのラインで製造されたかを記録で遡る。金属探知機の記録を確認し、金属片が除去されていたかを検証、異物が混入した可能性のあるロットを特定し、出荷先リストの確認、出荷先に連絡し、影響を受けた製品をすぐに回収などがが求められます。
Part 2:HACCP(ハザード制御)
HACCPは、食品の製造過程で発生する可能性のある危険(食中毒や異物混入、アレルギー反応など)を予測し、問題が起こらないように管理する仕組みです。JFS-B規格では、HACCPの12手順7原則に基づいた管理が求められます。
HACCPの12手順
①HACCPチームを作る
食品安全の知識がある人を集め、HACCPの管理を担当するチームを作ります。
②製品の特徴を明確にする
どんな食品を作るのか(材料、加熱温度、賞味期限など)をまとめます。
③食品の用途を確認
その食品を誰が、どのように食べるのかを確認します。(例:加熱が必要か、そのまま食べるのか)
④製造工程を整理
食品がどのように作られるのか、原材料の受け入れから出荷までの流れを図にする(フローダイアグラム)。
⑤製造工程を実際に確認
フローダイアグラムが正しいか、現場でチェックし、必要なら修正する。
⑥危害要因(ハザード)を分析
食品の安全に影響する危険をリストアップする。(例:食中毒菌、異物混入、化学物質)
⑦重要管理点(CCP)を決める
最も重要な管理ポイント(CCP)を決める。(例:加熱温度、冷却時間)
⑧CCPの管理基準を設定
食品の安全を守るための基準(温度、時間、pHなど)を決める。(例:肉の中心温度を75℃以上にする)
⑨CCPの監視方法を決める
基準を守れているか監視する方法を決める。(例:温度計で測定、記録)
⑩異常が起こった場合の対応
基準を満たさなかった場合、どう対処するかを決める。(例:温度が足りなければ再加熱)
⑪確認作業(検証)
HACCPが正しく運用されているか、定期的に確認する。(例:温度記録のチェック、サンプル検査)
⑫記録を残す
HACCPの管理状況を記録し、トラブルが起きたときにすぐに対応できるようにする。
HACCPの7原則
①危害要因の分析
食品にどんな危険(ハザード)があるかを考え、リストアップする。(例:細菌、異物、アレルゲン)
②重要管理点(CCP)の決定
食品の安全を守るために、必ず管理すべきポイント(CCP)を決める。
③管理基準の設定
CCPで守らなければならない基準(温度・時間など)を決める。
④CCPの監視方法の確立
基準を守れているかどうかを毎日チェックする方法を決める。
⑤異常が起きた場合の是正措置
基準を守れなかったときにどんな対応をするかを決める。
⑥検証方法の確立
HACCPが正しく機能しているか、定期的に見直す。
⑦記録の作成と管理
HACCPの実施状況を記録し、万が一の問題が発生したときに備える。
Part 3:GMP(一般衛生管理)
GMPは、食品製造の基本的な衛生管理を行う仕組みです。以下主要な箇所を抜粋して解説します。
① 汚染リスクの管理(GMP8)
食品が物理的・化学的・生物的な汚染を受けないよう管理する必要があります。
例えば、工場内の水道の蛇口をこまめに清掃し、雑菌の繁殖を防ぐことで、衛生的な環境を維持します。
② 交差汚染の防止(GMP9)
食品の製造工程において、異物混入やアレルゲンの交差汚染を防ぐことが求められます。
例えば、アレルゲン(小麦・乳製品)を含む食品と含まない食品の製造ラインを完全に分けることで、アレルギー事故を防止します。
③ 輸送の衛生管理(GMP15)
食品を安全に輸送するため、清潔な輸送環境を確保する必要があります。
例えば、冷蔵食品を輸送するトラックの温度を常に5℃以下に維持し、温度記録を残すことで、食材の品質を確保します。
JFS-B取得までの流れ
JFS-Bの取得には、自社のルールを元に、食品安全管理の仕組みを整備、追加修正して構築します。
具体的には、以下のような取り組みを行います。
①キックオフ
全員参加の共通意識を持つためのイベントです。
経営層(社長、工場長など)から従業員に向けて、HACCPチームへの全面協力を業務指示として発言いただけると効果的です。
②手順類の作成
食品安全マニュアル(作成しない場合もありうる)、HACCP文書(フローダイヤグラム、ハザード分析、ハサッププラン、製品説明書)、その他必要な手順書、帳票類の作成、従業員への教育
③手順に基づく運用
食品安全マニュアル、HACCP文書等に基づく運用、記録作成を行います。
例えば、HACCPの重要管理点(CCP)である加熱温度の記録を残したり、異物混入のリスクを減らすためのチェックリストを活用したりします。
この段階では、従業員全員がJFS-Bのルールを理解し、日常業務の中で正しく運用できているかが重要です。
食品安全の方針や手順を掲示したり、定期的にミーティングを開いたりして、運用の定着を図ります。
④運⽤状況の確認
マニュアルやHACCP文書通りに運用できているかの確認をします。必要により、従業員への再教育、文書類の加筆修正
⑤監査を受ける
JFS-B監査を受けます。監査員が現地にて作業現場で観察やヒアリング、書類確認を行います。
指摘があれば対応し、審査員へ報告します。
⑥判定通知、適合証明取得
監査会社内の判定会議で合格判定を受け、判定通知書、適合証明書を入手する。
監査に合格すると、JFS-Bの適合証明書が発行されます。
この証明書は、食品安全管理の基準を満たしていることを証明し、取引先や消費者に対する信頼性の向上につながります。
⑦適合証明取得後
一度取得すれば終わりではなく、毎年一回、定期的な監査を受け、3年に一度は更新監査を受けながら、継続的に食品安全管理を改善していくことになります。
JFS-Bの取得費用
取得にはコンサル費用や監査費用がかかります。
ここでは、JFS-Bの取得に必要な費用と、その特徴について説明します。
1.JFS-Bのコンサル費用
JFS-Bを取得するためには、企業だけで準備するのは大変なため、専門のコンサルタントのサポートを受けるのが一般的です。
ISOコム株式会社では、月額9万円~のコンサルティングサービスを提供しており、取得までに8~12ヶ月程度、約108万円~の費用がかかります。
この費用には、以下のようなサポートが含まれます。
①食品安全のルール作り(HACCPやGMPの導入)
②文書作成の支援(必要な記録や手順書の作成方法の説明、テンプレートの提供、作成結果の添削指導など)
③従業員教育の実施(食品安全の知識向上)
④JFS-B取得までのサポート(監査前の準備や運用状況の確認、監査指摘のフォロー等)
このように、コンサルタントの支援を受けることで、それまでの工場内で運用をベースにした最短距離で効率的にJFS-Bを取得することができます。
2.JFS-Bの監査費用
JFS-Bを取得するためには、第三者機関の監査を受ける必要があります。
監査には、初回監査・維持監査・更新監査の3種類があります。50名未満の1工場の場合、費用の目安は以下のとおりです。
①初回監査費用(適合証明取得時)
25万円~ JFS-Bの基準を満たしているか確認し、適合していれば認証が発行されます。
②維持監査費用(毎年の確認)
20万円~ 適切な管理が続けられているかチェックし、不適合があれば改善を指導します。
③更新監査費用(3年ごと)
25万円~ 3年毎の更新監査時に、すべての管理状況を再確認し、基準を満たしていれば更新され、適合証明書が再発行されます。
監査費用は、工場の規模や業態によって変動することがありますが、一般的には上記の範囲内で収まります。
3.ISOコム株式会社の強み
JFS-Bの取得を目指す企業にとって、ISOコム株式会社は「コンサル」と「監査」の両方を行えるため、一貫したサポートを受けられるのが大きなメリットです。
①コンサルティング
JFS-B取得に向けた仕組み作り、文書作成、従業員教育、監査での指摘を合格までサポート
②監査の実施
適合証明取得のための第三者監査を実施
通常、コンサル会社と監査会社は別々ですが、ISOコムならワンストップで対応できるため、スムーズに認証取得が可能です。
まとめ
JFS-Bの要求事項のポイントを監査時の指摘ポイント、お分かり頂いたでしょうか。
この規格は、ISOなどの他の規格に比べ、短くまとまっていますが、その分重要な内容が短く凝縮されています。
規格やガイドラインは、JFSMのウェブサイト(https://www.jfsm.or.jp/)から無料でダウンロードできます。
HACCPの下地のある組織様は、取組む順序としてFSM→HACCP→GMPと規格順に攻略するのが正攻法と言えると思いますね。
規格を正しく理解しておかないと、監査で思わぬ不適合が、沢山の対策に追われる、監査合格も予定よりもどんどん伸びてしまうかも。お金も労力も二度手間になってしまい兼ねません。
スリムな仕組みを最低限の労力で作り、効率よく監査に合格し、早くお客様の信頼を高めたい、取引継続をしていきたい。そんなあなたの会社をISOコムは強力にサポートします。
もちろん、HACCP認証だけのサポートも可能です。
JFS-B規格、HACCPが気になる方は、今すぐお問い合わせフォームからご相談を!!
ISOコム株式会社お問合せ窓口 0120-549-330
当社ISOコム株式会社は各種ISOの新規取得や更新の際のサポートを行っているコンサルタント会社です。
ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方はぜひご連絡下さい。