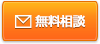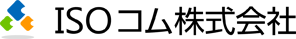食品衛生責任者の取得方法。何ができるの?
投稿日:2025年7月6日 最終更新日:2025年7月24日

こんにちは。ISOコム株式会社のマネジメントコンサルタント、青森誠治です。
今回は、食品衛生責任者の役割、資格の取得方法、講習内容、そして実務でのポイントについて詳しく解説します。
食品衛生責任者は、食品を取り扱う施設の安全を守る重要な役割を担います。
この記事では、初心者の方にも分かりやすく、かつ実践的な情報を提供し、食品衛生責任者を目指す方や事業者の方に役立つ内容をお届けします。
Contents
食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは、食品を取り扱う施設の衛生管理を統括する責任者のことです。食品衛生法施行条例に基づき、以下の役割が定められています。
・営業許可施設ごとの設置:飲食店、食品加工工場、給食施設、スーパーマーケットなど、保健所から営業許可を受けた施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を任命する必要があります。
・衛生管理の取りまとめ:営業者(社長、店長、オーナーなど)の指示のもと、施設全体の衛生管理を統括します。例えば、食材の保管温度の管理や清掃手順の徹底など、具体的な衛生対策を推進します。
・食中毒予防の提案:食中毒や異物混入などの事故を防ぐため、施設の改善点を営業者に提案します。営業者はその提案に基づき、必要な改善を行う義務があります。
・法令順守と知識の更新:食品衛生法や関連法規の改正に注意し、違反がないよう管理します。また、保健所や食品衛生協会が開催する衛生講習会に定期的に参加し、最新の知識を維持する必要があります。
・チームワークの促進:食品衛生責任者は、衛生管理を一人で担うのではなく、職場の全員が衛生意識を持つようリーダーシップを発揮します。例えば、従業員への教育や役割分担を通じて、職場全体で衛生管理に取り組む環境を整えます。
食品衛生責任者の役割は、単なる管理職ではなく、職場全体の衛生意識を高めるリーダー的存在です。
「衛生管理は食品衛生責任者の仕事だから自分は関係ない」という考えが広まると、衛生管理の質が低下します。そのため、職場の全員が協力し合う意識を持つことが重要です。
食品衛生責任者資格の取得方法
食品衛生責任者の資格を取得する方法は、大きく分けて2つあります。以下で詳しく説明します。
1. 特定の資格保有者
以下の資格を持っている方は、食品衛生に関する知識があるとみなされ、追加の講習を受けずに食品衛生責任者に任命されることができます。
・ 栄養士
・ 調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者または食品衛生監視員となる資格を有する者(医師、薬剤師、獣医師など)
これらの資格は、取得時や業務の中で食品衛生の知識が求められるため、食品衛生責任者としての役割を果たす準備が整っているとみなされます。
2. 食品衛生責任者養成講習会の受講
上記の資格を持っていない場合でも、各都道府県や自治体が主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます。この講習会は、食品衛生の基礎から実践的な知識までを学ぶ機会です。
受講資格
受講資格は比較的緩やかで、例えば東京都の場合、以下の条件を満たせば受講可能です。
・満17歳以上(高校生は不可)
・住所地、勤務地、従事経験、学歴などは問わない
・外国人の方は、日本語が理解でき、在留カードまたは特別永住者証明書があれば受講可能
日本語の理解度については、明確な基準(例:JLPT N2以上など)は設けられていませんが、講習内容は専門的な内容を含むため、ある程度の日本語力が必要です。
一部の地域では、英語や多言語対応の講習会が提供される場合もありますが、事前に確認が必要です。
講習会の申し込みと開催情報
講習会は各都道府県の食品衛生協会や保健所が主催し、開催頻度や申し込み方法は地域によって異なります。
例えば、東京都食品衛生協会では、年に数回、対面またはオンラインで講習会を開催しています。以下は、一般的な申し込みの流れです。
1. 情報収集:地域の食品衛生協会のウェブサイト(例:東京都食品衛生協会 https://www.toshoku.or.jp/)や保健所のホームページで開催日程を確認。
2. 申し込み:オンラインまたは郵送で申し込み。定員制のため、早めの申し込みが推奨されます。特に春先は新入社員の団体申し込みで混雑することがあります。
3. 受講料:受講料は地域により異なりますが、約8,000円~12,000円程度が一般的です(例:東京都は10,000円前後)。
4. 開催形式:コロナ禍以降、オンライン講習も増えていますが、対面講習が主流の地域もあります。
具体的な開催情報や申し込み方法は、地域の食品衛生協会に問い合わせるか、ウェブサイトで確認してください。
例えば、大阪府では大阪食品衛生協会(https://www.osaka-shokuhin.or.jp/)が情報を公開しています。
食品衛生責任者講習の内容
講習会は、食品衛生の基礎知識を学ぶための6時間のプログラムで構成されています。以下は主な内容です。
・公衆衛生学(1時間):伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生など、公衆衛生の基礎を学びます。例として、ノロウイルスやサルモネラ菌の感染経路や予防方法が含まれます。
・衛生法規(2時間):食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準など、関連法規を学びます。営業許可の取得手続きや違反時の罰則についても触れられます。
・食品衛生学(3時間):食中毒の原因(微生物、化学物質、異物混入など)、食品の安全な取り扱い、施設の衛生管理、自主管理の方法を学びます。例えば、冷蔵庫の温度管理(5℃以下)や従業員の手洗い手順などが具体例として挙げられます。
講習は丸1日かけて行われ、講義形式で進められます。受講後には確認テストが行われることが一般的です。
テストは講習内容を理解していれば解答可能な問題で構成されており、合格率は高い傾向にあります。
合格すると、当日中に修了証が発行されます。この修了証は、営業許可の申請時に提出が必要なため、大切に保管してください。
なお、修了証には有効期限がなく、平成9年4月以降に取得したものは全国で有効です。そのため、早めに受講しておくと、将来の転職や新たな事業開始時にスムーズに対応できます。
資格取得後の実務とHACCPの義務化
食品衛生責任者の資格を取得することはスタートラインに立つことに過ぎません。実際の業務では、以下のような役割が求められます。
実務での具体的な役割
食品衛生責任者は、施設の衛生管理をリードします。以下は、飲食店や食品加工工場での具体例です。
・食材管理:冷蔵庫や冷凍庫の温度チェック(例:冷蔵5℃以下、冷凍-18℃以下)、賞味期限の確認。
・施設の清掃:厨房の床や調理器具の洗浄スケジュールを設定し、実行を監督。
・従業員教育:手洗いや衛生的なユニフォーム着用の徹底を指導。定期的な衛生講習を企画。
・記録管理:衛生点検の結果や改善措置を記録し、保健所の監査に備える。
これらの業務は、食品衛生責任者だけで完結するものではなく、職場の全員が協力して取り組む必要があります。例えば、チェックリストを作成し、従業員に役割を割り当てると効率的です。
HACCPの義務化について
2021年6月から、食品衛生法の改正により、すべての食品事業者にHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)に基づく衛生管理が義務化されました。HACCPは、食品の安全性を確保するための科学的な管理手法で、以下のステップが含まれます。
1. ハザード分析:食中毒や異物混入のリスクを特定(例:生肉の細菌汚染)。
2. 重要管理点(CCP)の設定:リスクを制御するポイントを決める(例:加熱調理の温度)。
3. 管理基準の設定:具体的な基準を定める(例:中心温度75℃以上で1分間加熱)。
4. モニタリングと記録:基準が守られているか確認し、記録を残す(例:温度計での測定記録)。
食品衛生責任者は、HACCPの計画立案や実行の中心的な役割を担います。
例えば、レストランでは、食材の受け入れ時の温度チェックや調理後の冷却手順を記録する仕組みを作ります。記録は保健所の監査時に提出が必要なため、正確さが求められます。
HACCPの導入は最初は負担に感じるかもしれませんが、食中毒予防や顧客の信頼向上につながります。食品衛生責任者がリーダーシップを発揮し、職場の全員で取り組むことで、スムーズな運用が可能です。
第三者認証(ISO22000、FSSC22000、JFS-B規格)の活用
近年、ISO22000、FSSC22000、JFS-B規格などの第三者認証を取得する企業が増えています。これらの認証は、HACCPをさらに進化させた衛生管理の仕組みを構築し、外部の審査員による客観的な評価を受けるものです。認証取得のメリットは以下の通りです。
・信頼性の向上:顧客や取引先に対し、安全性の高い食品を提供していることを証明。
・食品事故の予防:微生物汚染、賞味期限の誤表示、アレルギー表示ミス、異物混入などのリスクを低減。
・国際競争力の強化:特に輸出を視野に入れた企業にとって、国際規格の認証は有利。
ただし、認証取得にはコスト(審査費用、コンサルティング費用など)や運用負担(定期的な書類作成、内部監査など)が伴います。認証取得を検討する場合は、以下の点を確認してください。
・自社の規模や業態に適した規格を選ぶ(例:中小企業ならJFS-B規格が導入しやすい)。
・認証取得にかかる期間(通常6ヶ月~1年)と費用を事前に見積もる。
・認証後も継続的な運用が必要なため、社内のリソースを確保。
ISOコム株式会社では、ISO22000やFSSC22000の取得支援を行っています。規格の要求事項を正確に理解し、審査員の視点を取り入れた効率的な仕組み作りをサポートします。興味がある方は、弊社お問い合わせ窓口(0120-549-330)かお問い合わせフォームまでご連絡ください。
補足:地域差や最新情報の確認
食品衛生責任者養成講習会は、地域によって開催頻度や受講料が異なります。以下は主要都市の例です(2025年7月時点の想定)。
・東京都:東京都食品衛生協会が月1~2回開催。受講料約10,000円。オンライン講習も一部実施(詳細:https://www.toshoku.or.jp/)。
・大阪府:大阪食品衛生協会が年数回開催。受講料約9,000円~11,000円(詳細:https://www.osaka-shokuhin.or.jp/)。
・福岡県:福岡県食品衛生協会が不定期開催。受講料約8,000円~10,000円。
コロナ禍以降、オンライン講習が増加していますが、対面講習が主流の地域もあります。最新情報は、各地域の食品衛生協会のウェブサイトで確認してください。
また、食品衛生法やHACCPの運用基準は定期的に改正されるため、最新の法令を把握することが重要です。
例えば、2021年のHACCP義務化以降、簡易的なHACCPプランが中小事業者向けに導入されるなど、柔軟な対応が進められています。食品衛生協会や保健所のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。
まとめ
食品衛生責任者は、食品の安全を守る重要な役割を担います。資格取得は、特定の資格を持つ場合を除き、6時間の養成講習会を受講することで可能です。
講習内容は実務に直結する知識が中心で、修了証は全国で有効です。
資格取得後は、HACCPの導入や職場の衛生管理の推進が主な任務となり、チームワークが成功の鍵です。第三者認証の取得を検討する場合は、コストとメリットを慎重に比較し、専門家の支援を活用すると効率的です。
食品衛生責任者を目指す方や、事業者として衛生管理を強化したい方は、まずは地域の食品衛生協会に問い合わせ、講習会の予定を確認してください。
早めの行動が、スムーズな資格取得や事業運営につながります。
ISOコム株式会社では、衛生管理の仕組み作りや認証取得のサポートを提供しています。お気軽にご相談ください(お問い合わせ:0120-549-330)。