難易度高め?FSSC22000を取得する方法と流れ
投稿日:2022年1月18日 最終更新日:2026年1月28日

皆さん、こんにちは。ISOコムの芝田有輝です。
今回は、FSSC22000の認証取得の難易度と取得方法についてお話しします。
Contents
FSSC22000とは?
FSSC22000は、食品の安全を守るための国際的なルールで、食品安全認証財団(FSSC)が運営しています。また、世界的な食品安全の基準を決める「GFSI」にも認められている認証の一つです。
この認証をとれば、企業は「うちの食品は安全に作られています!」を世界にアピールできます。
しかし、「どうやって取得すればいいの?」「ISO22000より難しそう…」と不安に思う企業も多いようです。
FSSC22000には、衛生管理をしっかり整え、ルール通りに運用し、専門機関の審査を受ける必要があります。
FSSC22000の構成とは
FSSC22000は、食品の安全を確保するための国際的な認証規格で、以下の3つの要素から構成されています。
①ISO22000
これは、国際標準化機構(ISO)が定めた食品安全マネジメントシステムの国際規格です。食品を製造・提供する企業が、食品の安全性を管理・維持するための枠組みを提供しています。
②前提条件プログラム(PRPs):ISO/TS22002
PRPsは、食品の安全を確保するための基本的な条件や活動を指します。
例えば、工場内の清掃や設備の衛生管理、従業員の衛生教育などが含まれます。ISO/TS22002は、これらの前提条件プログラムを具体的に示した技術仕様書で、食品製造業者が安全な食品を生産するための詳細なガイドラインを提供しています。 
③追加要求事項
FSSC22000独自の追加要求事項で、ISO22000やPRPsだけではカバーしきれない部分を補完します。
例えば、食品防御(フードディフェンス)や食品偽装の防止、アレルゲン管理などが含まれます。
これらは、食品の安全性をさらに高めるための重要な要素となっています。
これら3つの要素が組み合わさることで、FSSC22000は食品業界における包括的な食品安全マネジメントシステムを構築し、消費者に安全で高品質な食品を提供することを可能にしています。
FSSC22000の難易度とは?

FSSC22000は難しい、というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか?
確かに、FSSC22000はGFSI(Global Food Safety Initiative:国際食品安全イニシアチブ)承認の食品安全認証ですので、どんな会社でもすぐに合格できる、というレベルのものではありません。
GFSIは世界中の食品安全の認証を評価していて、認証されたものは国際的に通用するレベル、ということになるんです。
以下に、FSSC22000の難度が高いとされる背景に触れてみましょう。
1.規格の改定頻度が高い
FSSC22000は、食品の安全に関する新しい問題やリスクが見つかると、その対策を取り入れるためにルールを見直します。
この見直しは、約1~2年ごとに行われることが多いです。
例えば、新しい食中毒の原因が発見された場合、その防止策をルールに追加します。
これにより、最新の情報に基づいた安全な食品作りが可能となります。
2.無通告審査
FSSC22000では、認証登録後、毎年審査を受けていきます。
3年に一度、突然審査員が工場を訪れて、衛生管理や製造過程が適切かをチェックします。
これにより、会社は常に高いレベルの衛生管理を維持することが求められます。
いつ審査があるか事前に知らせずに突然審査員が工場を訪れて、衛生管理や製造過程が適切かをチェックします。
審査員が来るからルールを守るのではなく、普段から安全なルールを守る体制を維持しておく必要があります。
例えば、ある食品工場では「衛生管理」をしっかりやるルールがあります。
ただし、普段は手洗いをしっかりしないスタッフがいます。
もし、事前審査の予定がわかっていたら、一日だけ慎重に洗うかも知れません。
そういうことが3年に一度の審査では通用しない。
常にルールを守る体制が定着していることが重要になります。
認証が難しいと感じたらコンサルに相談すべき
このようにFSSC22000を自力で取得するのは難しい面があります。そのため、弊社のようなISO取得専門のコンサルタントに相談することがスムーズに取得できる1番の方法です。
弊社のサービスや費用をご覧になりたい方はこちらを参照してください。
FSSC22000の取得ステップ① 仕組み・ルールを作る
FSSC22000を取得するには、食品の安全を守るための仕組み・ルール(食品安全マネジメントシステム)を作る必要があります。
これは、工場の中を清潔に保つ、異物が入らないようにする、食品の温度を適切に管理する など、
安全な食品を作るための仕組みです。
でも、実は難しいことばかりではなく、すでにやっていることがFSSC22000の仕組み・ルールに合っている場合も多いのです。
1.会社全体で取り組むための食品安全チーム作り
最初に、FSSC22000を取得するためのHACCPチーム(食品安全チーム)を作ります。
HACCPチームは、食品の安全を守るために作る専門チームです。
工場長、品質管理、製造担当、設備管理、衛生管理、仕入れ担当などみんなで意見を出し合い、危険を防ぐルールを作ります。
そして、「FSSC22000を取得しよう!」と社内全体に発表し、みんなで協力する雰囲気を作ることが大切です。
具体例:
・お菓子工場なら、まず、工場の責任者が中心となり、原材料を管理する人、製造工程を知っている人、品質チェックをする人など、工場のいろいろな仕事を担当している人を集めます。
例えば、チョコレート工場なら、カカオの仕入れ担当、チョコを作る職人、包装する人、衛生管理の担当者などが入ります。
みんなで協力して、どんな危険があるか考え、対策を決めるのがHACCPチームの役割です。
2.今のやり方を確認し、準備をする
次に、今の会社の食品管理の状況を確認します。
たとえば、どのように食材を保管しているか、製品がどのように作られているか(フローダイアグラム)、どんな衛生管理をしているかを調査します。
また、食品の原材料がどこから仕入れられているかも確認します。
たとえば、「いつも買っているお肉が足りないから、見たことのない業者から適当に仕入れる」ということはしませんよね?
信頼できる業者から買い、もし賞味期限が切れていたら交換してもらうはずです。
実は、これもFSSC22000のルールの一部なのです。
具体例:
・パン工場なら、「生地を作る → 発酵させる → 焼く → 包装する」という流れを図にする
・お弁当工場なら、「食材の仕入れ → 調理 → パック詰め → 出荷」の流れを整理する
3.食品安全の方針や目標を決める
次に、「どうすれば安全な食品を作れるか」を会社の方針として決めます。
たとえば、「異物混入ゼロを目指す」「お客様に安心して食べてもらえる食品を作る」などです。
この方針を具体的に目標に置き換えて取り組みます。会社のルールとして全社員が知っておく必要があります。
具体例:
給食工場の方針なら、「すべての食品を安全に管理し、異物混入や食中毒を防ぐ」「法律や衛生基準を守り、安心できる食事を提供する」。
目標なら、
1.異物混入ゼロを目指す → 食材を使う前に異物チェックを徹底し、髪の毛や虫が入らないようにする。
2.衛生管理を強化する → 手洗いルールを守り、調理器具や作業場を毎日消毒する。
3.適切な温度管理 → 調理後の食事を決められた温度で保管し、細菌の増殖を防ぐ。
などが考えられます。
4.前提条件プログラム(PRP)の構築
まず、工場全体の衛生管理を徹底します。例えば、作業場の清掃や従業員の手洗い、設備の点検など、基本的な衛生管理を行います。
4.1 ハザード分析の実施
次に、製造工程で発生し得る危害(ハザード)を特定し、その予防策を検討します。
例えば、生魚を扱う工場では、以下のようなハザードが考えられます。
生物学的ハザード:魚に付着する細菌や寄生虫など。
物理的ハザード:魚の骨や異物の混入など。
化学的ハザード:洗浄剤や消毒液の残留など
4.2 HACCPプランの策定
特定した危害(ハザード)に対する具体的な管理手順を定めます。
例えば、生魚の細菌を防ぐために、冷蔵庫の温度を適切に設定し、定期的に温度を確認するなどの対策を講じます。
これらの取り組みにより、食品の安全性を高めることができます。
4-3. 必要な書類を作る
以下のような文書を整備し、ルールや手順を明確にすることが重要です。
1.食品安全方針:
会社や工場のトップが策定する、食品安全に関する基本的な考え方や取り組みの方向性を示す文書です。
例えば、「私たちは安全で高品質な食肉製品を提供し、消費者の健康を守ります」といった内容です。
2.食品安全目標:
食品安全方針を実現するための具体的な目標を設定し、その達成に向けた指針を示す文書です。
例えば、「異物混入ゼロを目指す」「製品の鮮度を保つために適切な温度管理を徹底する」といった目標を設定します。
3.製造工程図(フローダイヤグラム):
原材料の受け入れから最終製品の出荷までの全製造工程を視覚的に示した図です。
例えば、「原材料受け入れ→洗浄→カット→加熱→包装→出荷」といった流れを図示します。
5.ハザード分析表:
各工程で発生し得る危害要因(ハザード)を特定し、そのリスク評価と管理手段をまとめた表です。
例えば、「カット工程での金属片混入のリスク→金属探知機で検査」といった内容を記載します。
6.HACCPプラン:
特定した重要管理点(CCP)における管理基準、モニタリング方法、是正措置、検証方法、記録の保存方法などを詳細に記載した計画書です。
例えば、「加熱工程の温度を75℃以上に保つ→温度計で定期的に確認→温度が低い場合は再加熱」といった手順を定めます。
7.製品説明書:
各製品の名称、原材料、製造方法、保存条件、賞味期限などの詳細情報を記載した文書です。
例えば、「鶏肉ソーセージ:原材料は鶏肉、塩、香辛料。製造方法は加熱処理。保存は冷蔵で、賞味期限は製造日から10日間」といった内容です。
8.前提条件プログラム(PRP):
衛生管理や施設の維持管理、従業員の衛生教育など、基本的な環境や条件を整備するための手順や基準を定めた文書です。
例えば、「作業場の清掃は毎日行う」「従業員は作業前に手洗いを徹底する」といったルールを設定します。
9.施設配置図(レイアウト図):
工場内の設備や作業エリアの配置を示し、動線の最適化や衛生管理の向上に役立つ図面です。
例えば、「原材料保管エリア」「加工エリア」「包装エリア」を明確に区分けし、交差汚染を防ぐ配置を考えます。
10.作業手順書:
各作業工程における具体的な手順や方法を詳細に記載した文書です。
例えば、「原材料の受け入れ検査手順書」「製造設備の洗浄・消毒手順書」「温度管理手順書」などがあります。
11.食品安全マニュアル:
上記の方針や手順をまとめた総合的な文書で、会社や工場全体の食品安全管理の基本となるものです。
これらの文書を整備し、会社や工場全体で共有・遵守することで、FSSC22000の認証取得と効果的な運用が可能となります。
FSSC22000の取得方法② 仕組み・ルールを運用する
仕組み・ルールができたら、運用してみましょう。
1.現場での運用:
作成した仕組み・ルール文書に基づき、現場で実際に作業を行います。
例えば、食品工場では、手洗いの手順や機械の清掃方法などがマニュアル化されています。
これらの手順を守り、日々の作業記録を残すことで、問題が発生した際に原因を特定しやすくなります。また、作業記録は、製品の安全性を証明するための重要な証拠となります。
2.内部監査の実施:
内部監査とは、社内の専門チームが、マニュアル通りに作業が行われているか、問題点がないかを証拠に基づいて確認する活動です。作業現場で行うことは非常に大切です。
例えば、ある食品工場では、定期的に現場をチェックし、改善点を見つけることで、製品の安全性を高めています。
内部監査の結果は、会社全体の食品安全の取り組みが有効かを評価するための重要な情報となります。
3.マネジメントレビューの実施:
内部監査の結果や日々の記録をもとに、経営層に食品安全の取り組みや成果を報告しま、経営層がその情報を元に、必要な決定や指示をします。
例えば、社員の力量や人数が不足していると判断した場合、追加の研修を計画したり、人員募集をするなどの対応を行います。
マネジメントレビューは、会社や工場や会社のトップが食品安全マネジメントシステムの有効性を評価し、継続的に仕組み改善するための重要な取り組みです。
FSSC22000の取得方法③ 審査を受ける
1.審査機関の選定
FSSC22000の認証を取得するには、審査機関を選ぶ必要があります。
審査機関は、会社や工場の規模や審査実績、所属する審査員の数などを基に選定します。
分からない場合には、弊社のようなコンサルタントに紹介してもらうのもよいでしょう。
例えば、食品業界での審査実績が豊富な機関や、自社の業界に詳しい審査員が在籍する機関を選ぶと良いでしょう。
また、審査費用やスケジュールの柔軟性も考慮することが重要です。
審査を受ける4~5ヶ月前には契約して、審査日を決定しておきましょう。
2.第一段階審査(ステージ1審査)
審査機関が決定したら、契約、審査日の決定、そして、第一段階審査が行われます。
これは、会社や工場が作成した食品安全方針やハザード分析表、HACCPプランなどの文書が、FSSC22000の要求事項に適合しているかを確認し、初期の運用状況を現地で確認するものです。
例えば、食品安全マニュアル、食品安全方針、目標、フローダイヤグラム、ハザード分析表、HACCPプラン、製品説明書などを見ます。
規格要求と合致しているか、不足や矛盾がないか、初期の運用状況は適切か、などを確認します。
作業現場も一通り確認し、次の第二段階審査に進める準備ができているかどうかを判断します。
不備があれば指摘事項が出され、次回の第二段階審査までに対応することが求められます。
3.第二段階審査
第一段階審査で、第二段階審査へ進めることができると判定されたら、大凡2ヶ月後に現第二段階審査が行われます。
この審査は、実際の作業現場を入念に回ります。
管理者へのインタビュー、実際の作業現場での状況の観察、作業者へのインタビュー等を行います。
定められたルール、手順に従って作業を行っているか、設備が適切に管理されているか、作業の証拠となる記録は適切に作成されているかなどを確認します。
例えば、作業手順書に基づき、従業員が適切に手洗いを行っているか、製造設備が定期的に清掃・消毒されているかなどを実際の作業現場を観察して、チェックしていくようなイメージです。
4.指摘対応/再発防止策(是正処置)
第二段階審査で不適合が指摘された場合、会社や工場は、その対応を期限付きで求められます。
指摘された問題を修正(有るべき姿に戻す)し、発生した仕組みの観点からの原因を特定し、
再発防止策の策定、実施を行います。
例えば、温度管理が不十分と指摘された場合、温度モニタリングシステムを導入し、定期的なチェックを行うなどの対策を講じ、その対策が、人が変わっても継続できるように、仕組み・ルールに落とし込みます。
5.認証取得
再発防止策(是正処置)が適切に実施され、そのことを審査員が認めてくれれば、審査機関内で実施される、判定会議(判定委員会)が行われます。
この場で、実施した審査結果を踏まえて、会社や工場を認証していいかを判定し、合格となれば、近日中にその旨の連絡が届き、FSSC22000認証の登録証が送られます。
見事、認証取得!ということになります。
おめでとうございます!!
6.定期審査と更新審査
認証取得後も、毎年審査が行われます。
これは、会社や工場が継続的に食品安全マネジメントシステムを適切に運用しているかを確認するためです。
例えば、年に一度の定期審査や、3年に一度は、予告なしの抜き打ち審査が実施されます。
これにより、会社や工場は、常に高いレベルの食品安全を維持し、継続的な改善を図ることが求められます。
以上のステップを経て、会社や工場はFSSC22000の認証を取得し、食品安全に関する信頼性を高めることができます。
これは、消費者や取引先からの信頼を得るだけでなく、会社や工場内部の業務効率化や従業員の意識向上にも貢献します。
まとめ
FSSC22000を取得するには、食品の安全を守るルールを作り、それをしっかり実行することが必要です。
しかし、すでにやっていることがFSSC22000の要求に合っている場合も多いので、難しく考える必要はありません。
会社全体で協力しながら、清潔な環境を保ち、食中毒や異物混入を防ぐ仕組みを作る ことが大切です。これによって、消費者に安全で美味しい食品を届けることができるのです。
食品業界での信頼性を高め、国際的な取引を拡大するために、FSSC22000の取得は非常に重要です。しかし、その取得プロセスは専門的で複雑なため、
FSSC22000の取得は当社にお任せください!
今回は、FSSC22000の難易度や取得する方法と流れについてお話ししました。
必ずしも難易度が高い、という訳ではありませんが、要求事項は様々な項目がありますので、適切なサポートが必要となります。
ISOコムなどの専門コンサルティングサービスを利用することで、効率的かつ効果的にFSSC22000の取得が可能となります。
ISOコムでは、皆さんの会社の仕事内容や状況を確認し、まずは何をしなければいけないのかを明確にしてから、皆さんと一緒に仕組み作りを行います。
そんなISOコムのコンサルに興味のある方は、今すぐお問い合わせフォームからご相談を!
*ISOコム株式会社お問合せ窓口* 0120-549-330
当社ISOコム株式会社は各種ISOの新規取得や更新の際のサポートを行っているコンサルタント会社です。
ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方はぜひご連絡下さい。
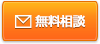
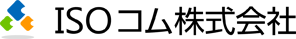



.jpg)
220607①.jpg)
