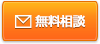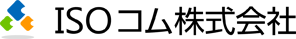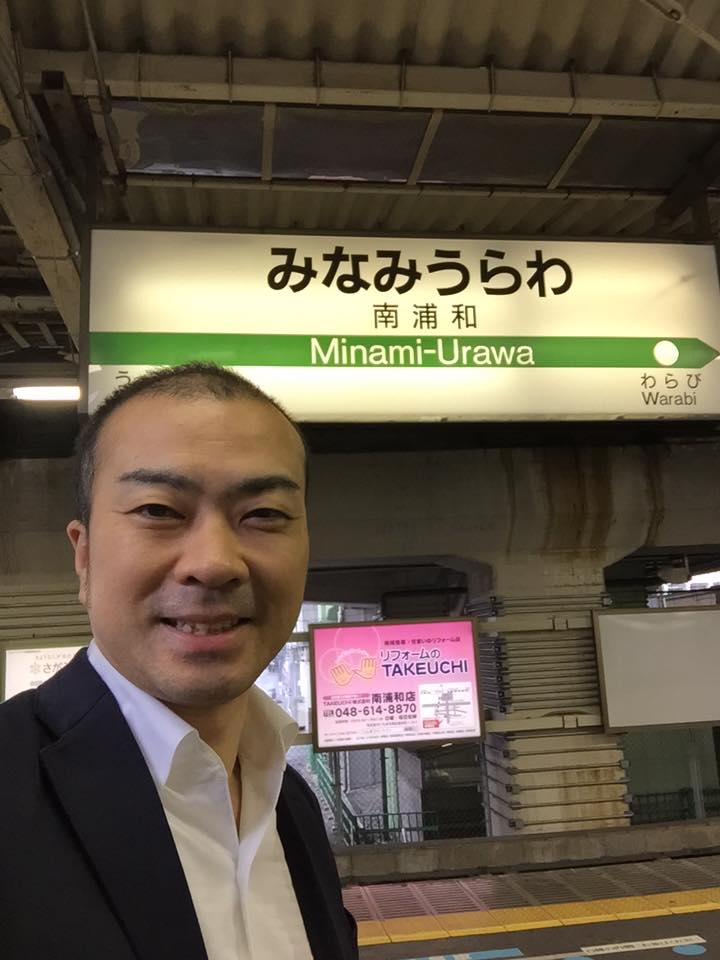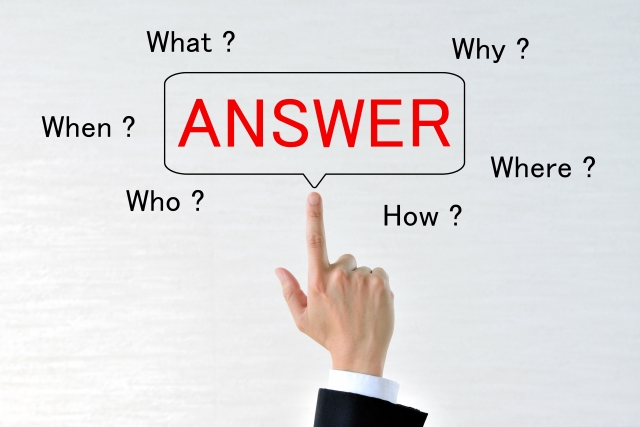ISO9001の取得方法と流れ
投稿日:2025年1月31日 最終更新日:2025年8月29日

こんにちは。ISOコムの芝田 有輝です。
今回は、「ISO9001の取得方法と流れ」について、お話ししてみたいと思います。
これを読めば、ISO9001を取得するにはどうすれば良いか、登録証入手までを一気に理解いただけるのではないかと思います。
Contents
ISO9001とは
ISO9001とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)が定めた品質やサービスの質を管理するための国際規格です。
1987年に初版が発行され36年が経過しており、その後改定を重ねて現在は2015年度版が発行されています。
ISO9001の規格の目指すところは、「顧客と合意した良質な製品やサービスを、継続して提供する仕組みを構築し、運用することで、顧客満足の向上を図る」ことにあります。
ISO9001に基づいて第三者審査機関から認証を受ける(後で詳しく説明します)ことで、企業や組織は自社の製品やサービスの質に対する信頼性を客観的に証明することができます。
そのため、取得していない企業や組織に比べて、発注者に選んでもらいやすくなったり競争優位の立場を築くことが期待できます。
ISO9001を取得するとは?
ISO9001を取得するとは、企業や組織がISO9001の規格が要求していることを満たしているかどうかを第三者に認定してもらうことです。
具体的には、第三者審査機関に審査をしてもらいISO9001の認証を受けて合格し、登録証を入手するまでがゴールです。
登録証が第三者審査機関から発行されたら、郵送か手渡しで受け取ることになります。
また、第三者審査機関や審査機関が認定する機関のウェブサイトでISO9001を取得している企業や組織の情報が一般公開されます。
ISO9001の第三者審査制度とは?

(1)ISO9001の第三者審査制度とは?
第三者審査制度とは、ISO9001の認証を受ける企業や組織を客観的に評価する制度です。
製品やサービスが引き合い(発注)を受けてからお客様への引き渡される流れや、その後の活動を含めて審査されます。
つまりプロセス毎に質の高い管理が適切に行われているかどうかを客観的に評価されるわけです。
ISO9001は一度取得すると毎年審査を受け続ける必要があり、取得までには以下の2回の審査があります。
取得前の審査
取得前:第一段階審査
取得前:第二段階審査
取得後の審査
ISO9001取得後には、以下のように毎年審査があります。
取得1年目:定期(維持)審査1回目
取得2年目:定期(維持)審査2回目
取得3年目:再認証(更新)審査1回目
取得4年目:定期(維持)審査3回目
取得5年目:定期(維持)審査4回目
取得6年目:再認証(更新)審査2回目
取得7年目:定期(維持)審査5回目
・・・・・・・・
というように、3年サイクルで定期審査、定期審査、再認証審査を受け続けることになります。
(2)第三者審査とは?
ISO9001の認証取得をしたい企業や組織と利害関係のない第三者審査機関(認証機関とも言います)が、企業や組織に現地現認で審査を行うことを言います。
具体的には、第三者審査機関の審査員が企業や組織を訪問し、ISO9001の規格要求に沿ったルールや、それに従った運用をしているかをチェックします。
経営層や部門責任者、作業担当者などにヒアリングをしたり、作業現場を観察したり、文書や記録を確認したりします。
審査員は中立的な立場で審査を行うため、審査を行う企業や組織との過去の利害関係がないことを事前に審査機関内で確認され、問題なしと判断された人が選ばれます。
これにより、審査の客観性や信頼性が担保されると言えます。
(3)ISOの認定機関とは?
日本国内では、経済産業省の外郭団体である、「公益社団法人日本適合性認定協会(通称JABといいます)」がISOの管轄をしています。
ここが、第三者審査機関を認定していますので、JABが認定した審査機関であれば、国際間取引を行っている企業や組織がISO9001を取得しても十分な信頼性があると言えます。
日本ではJAB、イギリスではUKAS、アメリカではANABなど、各国で認定機関があり、相互に承認していますので、原則はUKASやANAB等から認定を受けた審査機関も信頼性があると言えます。
弊社の経験則で言いますと、JAB、UKAS、ANABのいずれかで認定を受けている第三者審査機関であれば問題ありません。
ISO9001の認証取得後にお客様との取得の信頼性が揺らぐことはまず無いと言えるでしょう。
また、国際間取引を主体にしている会社の場合には、UKAS認定を受けている審査機関がオススメです。
ISO9001取り組み開始までに決めることとは?

さあ、前置きが長くなりましたが、ISO9001取り組み開始までに決めることについて話を進めて参りましょう。
(1) 取得目的を明確にする
まずは、ISO9001の取得目的を明確にしましょう。
大凡の会社は、取引先や主要なお客様からの要請があって取得の検討を始めます。
・「ISO9001を取得する予定はありますか」
・「ISO9001を取得する時期を教えてください」
・「ISO9001を取得してください。そうしないと、今後取引が出来なくなります」
こういった要請があって仕方なくとるというのが大半ではないかと経験則的に思っています。
ただ、このままですと、ISO9001の取得自体が目的になってしまい、単なる経費や負担になってしまう可能性があります。
そうなると、「早く、簡単に、安く」という牛丼チェーンのキャッチコピーにも似たような感じで、取り組みを始めてしまう企業や組織が増えてしまいます。
これはこれで全否定するつもりはありませんが、このブログの前段でお話したとおり、ISO9001の規格の目指すところは、「顧客と合意した良質な製品やサービスを、継続して提供する仕組みを構築し、運用することで、顧客満足の向上を図る」ことにあります。
そのため、せっかくの取り組みで得られるメリットを獲得するチャンスを活かしていただくためにも、「ISO9001の取得の向こう側にある目的」を取り組む前に明確にしていただければと思います。
例えば、
・品質を改善したい
・品質保証体制を確立したい
・作業者によってやり方がばらついて、品質もばらつくのを抑えたい
・不良やクレームを減らしたい
・歩留まりをよくしたい
・二代目に引き継ぐにあたり家族経営から会社経営に移行したい
などです。
もちろん、「入札参加資格を得たい」「経営審査事項の加点が欲しい」という理由も多く、これはこれで最もです。
しかしこの目的ですと、ISO9001を取得することとイコールになりますので、「ISO9001を経営課題にどう活用していきたいのか」ということを、取得目的として考えていただければと思います。
また、新規顧客獲得や、市場拡大、というのもよく耳にする取得目的です。
しかしISO9001のお陰で取引開始が出来ても、結局はその後に納品する品質や提供するサービスの質で取引を継続してもらえるかが決まります。
そう考えると、ISO9001を通して何を改善していきたいのか、と言う目的を明確にすることが大切であると言えます。
(2) 適用範囲を決める
a) 適用製品、サービスを決める
目的が決まれば、ISO9001の適用範囲を決めます。
適用範囲とは、ISO9001の登録証にどんな文言を記載したいのか、ということとイコールになります。
ISO9001は、どの製品やサービスで取得するかを選ぶことが出来ます。
もちろん、会社や組織の全製品やサービスを適用範囲にして取得することも可能です。
どのお客様向けにISOの効果をアピールしたいのかによって、どういった製品やサービスでISO9001を取得するかは検討の余地があります。
少し具体的になってしまいますが、その製品やサービスの仕様や規格を自社で決めているのか、お客様の要求や既にある製品・サービス規格に従って製造・提供しているのかも
把握しておきましょう。
b) 対象事業拠点、所在地を決める
適用製品・サービスが決まれば、その製品やサービスの引き合いから引き渡し、その後の活動(保守、メンテナンス等)にどの事業所や部門が関わってくるのかを洗い出します。
ISO9001は製品やサービスの限定取得が可能なのです。
ただし、営業、設計、製造(サービス提供)、購買(調達)、検査、出荷(引き渡し)等をしている事業所や部門は全てISO9001の適用範囲に含める必要があります。
この辺りは、弊社のようなコンサルを使う場合にはコンサル会社に、コンサルを使わない場合には審査機関とよく相談してから契約しましょう。
(3) 推進事務局、トップマネジメント、各部門責任者(管理責任者)を決める
続いて、推進事務局、トップマネジメント、関連する部門の決定です。
a) 推進事務局の役割
事務局は、審査機関やコンサルタントとの連絡窓口、社内のISO9001に取り組む部門との連絡調整が主な役割です。
ISO9001取得までの先導役、取得後の調整役のようなイメージかなと思います。
b)トップマネジメント
トップマネジメントとはISO9001の最高責任者となる人を言います。
1つの会社であれば、経営層(社長や取締役など)が該当します。
この経営層には、最低限、取締役以上であることが望ましいと言えます。
執行役員でいいかどうかは、その方にどの程度の権限が与えられているかによります。
ISO9001の要求事項の中に、事業継続をしていく上でのリスク(懸念事項)と機会(チャンス)を決めて、リスクと機会に対する対策を打ち、効果を確認することが要求されています。
つまり、事業課題を明らかにして、課題解決の対策のためにリソース(人、モノ、金、情報等)を決めたり、再配分したりする権限を持つ人であることが必要な条件となります。
審査でも経営層に向けた審査では、次のような質問に回答する必要があります。
「品質方針はどのような意図を込めているのか」
「ISO9001を何のために取得したいのか」
「今後どのような会社にしていきたいのか。」
「その上で事業上の課題は何か」
「その課題解決のための対策は何か」
c)各部門責任者(管理責任者)の役割
現在のISO9001:2015では、いわゆる管理責任者を任命して、ISO9001の仕組みの構築や運用、継続的な改善、取り組みの結果や成果を経営層に報告する等をしてください、という要求はなくなりました。
しかし管理責任者以外のだれかがその役割を担うことは要求されています。
管理責任者を任命してもいいですが、その人にだけISO9001の活動を任せきりになってしまうことによって、関わる人全員での取り組みによる、品質改善等の効果が薄れてしまう可能性があります。
そのため、できればISO9001の要求毎に、部門毎に責任を分担することが望ましいと思います。(旧規格では、世界中で管理責任者にISOを押しつけてしまい、取得効果が薄れて返上に至ることが多く報告されているようです)
ISO9001仕組みの構築では、営業、設計、製造(サービス提供)、購買(調達)、検査、出荷(引き渡し)等を含めた仕事の仕組みを、「現状をベース」に作り込むことになります。
そのため、今どのように仕事をしているのかを、4W1Hで品質マニュアル等、ルールブックに明らかにしていくことになります。
このように各活動をしている部門責任者や、その活動に詳しい人には、ルールブック作りの際に積極的に参加してもらう必要があります。
(4) 取得時期、取り組み開始時期を決める
次に、ISO9001をいつ取得するか、取り組みをいつ開始するかを決めます。
a) ISO9001の取得時期
ISO9001の取得とは、第三者審査機関から「登録証」をもらい、第三者審査機関や認定機関のウェブサイトに、公表される状態を言います。
つまり、ISO9001の取得時期とは、いつ登録証が欲しいのか、時期を決めることになります。
大体の会社や組織では次のタイミングが多い傾向にあります。
・一日も早く
・年内
・年度内
特に多く見られるのは、年内、年度内です。
このことによって、10~12月、2~3月は、どの審査機関も繁忙期になっております。
この時期に審査員を確保することが困難な状況にあり、企業や組織の受審希望時期に添えないケースも多々発生しているようです。
ISO9001は認証取得が1つのゴールでありますが、その後長年ISO9001を運用していくことのスタートにもなります。
先にこのブログで言いましたように、ISO9001は、取得後に毎年審査を受ける必要があります。
いつ受けるのかと言いますと、先ほどISO9001取得までには以下の2回の審査があると言いました。
取得前:第一段階審査
取得前:第二段階審査
この取得前の第二段階審査を受けて、約1ヶ月後に審査機関の中で判定会議があります。
審査が適正であったか、企業や組織を認証登録していいかを判定され、合格となれば登録証が発行されます。
この登録証の発行日が「基準日」となります。
毎年この基準日を元に同じような時期に審査が行われ、更新審査はこの基準日の2~3ヶ月前に審査が行われます。
このような、毎年の審査時期が、繁忙期にかかっていたりすると、審査の対応や指摘の対応等の為に業務へ支障を与えかねません。
そのため、第二段階審査をいつ受けて登録証をいつもらうのかということは重要です。
ISO9001取得後の毎年の審査時期が繁忙期にかからないように事前に配慮しておくことをオススメします。
b) ISO9001の取得期間
1事業所、50名程度の事業者の場合、取り組み開始から大凡8~12ヶ月で取得が可能と言えます。
実際に弊社では、1規格で4ヶ月、2規格(ISO9001,14001)で6ヶ月で取得いただいたケースもあります。
ただし、あまり短期間での取得は日常業務への影響も出る可能性があるため、8~12ヶ月での取り組みをオススメしています。
ISO9001のシステム構築を自力で行うか、コンサルを使うか?

(1)取得時期を踏まえて考える
自力でISOを構築するかコンサルを使うかは、いつISO9001を取得したいのかによって決まると思います。
特に期限がない場合には、社内で営業、設計、製造(サービス提供)、購買(調達)、検査、出荷(引き渡し)等をしている有志を募るなどして、一緒に勉強しながら少しずつ仕組みを構築していくこともありかと思います。
その場合、できれば、前の会社でISO9001の事務局をしていた等、経験者が含まれていることが望ましいと思います。
期限が決められている場合には、プロのコンサルタントを使うことをオススメします。
お金はかかりますが、期限内で安心して取り組むことが出来ると思います。
弊社のサービスも一度ご検討ください。→ISO9001認証取得支援サービス
(2)自力構築か、コンサルを使うかの判断基準
私個人の23年程度の審査経験から言いますと、自力で仕組みを構築された企業様に第一段階審査で50~60程度の懸念事項を指摘として出すことがありました。
当然ながら適用範囲の大きさ、対象とする事業の数にもよります。
ただ、コンサルを使えば、第一段階審査での懸念事項は多くても20以内に収まるのではないかと思います。
なぜ自力構築に懸念事項が多いかと言いますと、ISO9001規格の解釈を間違って仕組みを構築されてしまうことにあると思います。
ISO9001の規格は、原文は英文で作成されており、日本文では財団法人日本規格協会が和訳して「JISQ9001」として発行しております。通常は、このJISQ9001規格を元に、仕組みを構築します。
読んでいただけると分かりますが、私たちが日常的に使う言葉というよりも、もっと表現が堅くて難しい表現が多く、読みやすい文章とは言えません。
そこで、色々と規格解釈本が出ていますが、この解釈も色々です。
実際には、審査機関内でも規格が発行されてから、解釈の統一を図り、審査員に共有させるための勉強会を何回も行っているのが現状です。
このような背景の中、ISOのまったくの素人である企業や組織の方が解釈本を片手に仕組みを構築した場合どうなるでしょう?
解釈違いによって、規格要求事項の意図とは異なるルールを作り、運用することが目に見えています。
そうなりますと、審査の段階で問題を指摘され対応に追われるのは間違いありません。
ただ、それも経験値のうちだと割り切れるようでしたら自社構築はアリだと思います。
お金がかかっても、最短ルートで自社にあった仕組みを短期間で構築したいということでしたら、コンサルタントを利用することをお奨めします。
ISO9001システム構築から取得までの流れとは?

ISO9001システム構築から取得までの流れとは、ざっと以下の4ステップになります。
弊社がお客様にご提案するときにも、このステップをいつどのように実施するのかを工程表に表してご説明しています。
(1) キックオフ
ISO認証取得に関わる人、全員参加の共通意識を持つためのイベントがキックオフです。
経営層(社長さんなど)に、推進事務局への全面協力を、「業務指示」として発言いただけると、推進事務局に任せきりになってしまうリスクを低減するのに効果的です。
(2) システム構築段階
システム構築の成果物は、品質マニュアルや、業務フロー、手順書、記録帳票等となります。
次の3つが大切です。
a)ISO9001規格要求事項の理解
b)仕事内容の確認と規格要求事項とのマッチング
c)品質マニュアル、業務フロー、手順書、記録帳票の作成
特に大切なことは、b)のマッチングです。
ここは規格要求事項の主旨をよく理解し、自社で似たような仕事をしていないか、該当しそうな記録がないかを細かく確認して当てはめていきます。
この当てはめが上手くいかないと後々問題になります。
ISO9001に対応したルールが分厚いモノになってしまい、ISOを維持する上での仕事や記録が増えて「お荷物」化していきかねません。
(3) システム運用段階
a) 社内説明会
社員さん向けに、品質マニュアル、業務フロー、手順書、帳票の使い方等を説明します。
b) システム運用
品質マニュアル、業務フロー、手順書通りに仕事をして、その証拠として記録を残します。
・日常業務
・事業課題に対する取り組み
・品質方針の周知、品質目標達成に向けた取り組み
・設備や測定器の点検や校正
・不良/クレーム発生時の記録作成、修正や再発防止の実施
・顧客満足情報の収集や分析等
c)内部監査員の養成
ISO9001では、「内部監査」といいまして、品質マニュアル、業務フロー、手順書等通りに仕事をしているか、効果があるかを確認することを社内の内部監査員が実施することを要求しています。
このための内部監査員の養成教育が必要です。
コンサルタントによる講習を受けるか、研修機関の講習を受けるかが多いですが、社内で内部監査の力量を持つ人が講師となって社内講習することでも可能です。
内部監査員養成講座は弊社でも行っております。気になる方はご相談ください。
d)内部監査の実施
そうして養成された内部監査員によって内部監査を実施します。
内部監査の計画書、チェックリスト、指摘事項をまとめたモノ、内部監査の報告書を作成します。
e)マネジメント・レビュー
トップマネジメントによる、仕組み運用のレビュー(見直し)です。
推進事務局が各部門から、ISO9001の運用証拠を集めて、ISO9001の運用の結果や成果を記録にまとめて、トップマネジメントに報告します。
報告を受けたトップマネジメントは、今後の事業運営のための改善につながる指示や決定をします。
この指示や決定も記録に残し、次回のマネジメント・レビューの時に活用します。
(4) 審査対応段階
内部監査、マネジメント・レビューを終えたら、いよいよ審査を受ける段階に入ります。
(審査機関によっては、内部監査、マネジメント・レビュー実施前に審査を実施する場合もあります)
a)第一段階審査
第三者審査機関の審査員が、皆さんの会社や組織を訪問します。
ISO9001の要求事項に従った仕組みが出来ているかを、品質マニュアルの中味の確認、経営層や事務局、各部門にヒアリングを行って確認します。
また、ISO9001の初期運用状況として、事業課題の決定、品質方針の決定・周知、品質目標の決定と取り組み状況、内部監査の実施状況、マネジメント・レビューの実施状況、作業現場の概要と観察等を
行います。
総合的に第二段階審査に進めていいかどうかの判断を行います。
現段階での懸念事項があれば、審査最終日に指摘として書面で提示されます。
この指摘は第二段階審査までに対応が必要になります。
b) 第二段階審査
第三者審査機関の審査員が、皆さんの会社や組織を訪問します。
・経営層、各部門長へ事業課題や品質目標達成に向けた取り組みや成果
・各部門へ引き合いから引き渡し、引き渡し後の活動(保守、メンテナンス等)に至る業務の詳細のヒアリングや、記録の中味の確認
・作業現場にて作業者へ業務手順や品質基準、手順と異なった作業をした場合の影響、品質目標に沿った活動をしているか等、詳細な質疑
・第一段階審査での懸念事項に対する取り組みの確認
この第二段階審査では、審査最終日に不適合指摘又は改善の機会(観察事項)が、書面で提示されます。
不適合指摘については全て対応する必要があり、対応後は担当審査員に状況を提出し、容認してもらう必要があります。
この不適合対応は、第二段階審査後のおおよそ翌月くらいに審査機関内で実施される判定会議までに行わなければなりません。
c)判定会議
審査が適正に行われたかどうかを審査機関内のルールに基づいて判断するのと同時に、企業や組織がISO9001を認証登録するのにふさわしいのかを判断します。
適正と判断されれば、判定合格通知が企業や組織に提出されます。
この段階で、皆さんの会社や組織のお客様や関係者にISO9001を取得したことを報告することが可能です。
d) 登録証の発行
判定会議で合格が出れば、そこから1~2週間程度で「ISO9001登録証」が企業や組織向けに発行され、郵送又は手渡しで提示されます。
必要であれば、皆さんの会社や組織のお客様や関係者にISO9001登録証のコピーを提出することが出来ます。
このとき、必ずどこに何部提出したのかを記録を残しておいてください。翌年の審査で確認される場合があります。
e) 公表
登録証の発行後、審査機関や認定機関のウェブサイトに、企業や組織がISO9001を取得したことの情報が公開されます。日本適合性認定協会(https://www.jab.or.jp/)
以上をもって、ISO9001認証が取得できた!ということになります。
費用についても確認しましょう
最後にISO9001を取得するために必要となる費用はこちらのリンクからご覧ください。
最初は審査機関に支払う料金、コンサルタントに支払う料金が発生します。
ISOを取得後は毎年の更新審査のための費用が発生することを知っておきましょう。
まとめ
ISO9001を取得しようとお考えの皆様の疑問へのお答えになっていますでしょうか。
ISO9001を取得するためにいろいろなステップがありましたね。
どれも大切であり1つでも欠けてしまったり足りなかったりすると審査合格ができずに、「再審査」を受けなくてはならないこともあり得ます。
これは通常の業務に大きく影響する可能性が高いです。
そのため、これまでの業務を元に追加業務や記録を最小限にしてスムーズに審査合格することをお望みであれば、弊社のようなISO支援コンサルティング会社にご依頼ください。
コンサルについてお見積など気になる方はお問い合わせフォームから弊社にご相談ください。
ISOコム株式会社お問合せ窓口 0120-549-330
当社ISOコム株式会社は、各種ISOの新規取得や維持、更新の際のサポートを行っているコンサルティング会社です。
ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方は是非ご連絡ください。