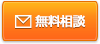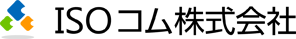HACCPとは何か。わかりやすく簡単に説明します。
投稿日:2023年9月13日 最終更新日:2026年1月22日
-3.jpg)
こんにちは!ISOコム株式会社の芝田 有輝です。
食品を作ったり販売したりする会社にとって、一番大切なことは「安全」ですよね。
せっかく作ったごはんやお菓子でも、食べた人が「お腹が痛い…」「気分が悪い…」なんてことになったら大変です。
そこで、今とても注目されているのが HACCP(ハサップ) という仕組みです。
「聞いたことあるけど、むずかしそう…」と思っていませんか?
大丈夫!この記事では、HACCPの意味や必要な理由、どうやって取り入れるのかを、具体例を交えながら、できるだけわかりやすく説明します。
Contents
HACCP(ハサップ)ってなに?
HACCPは、英語で「Hazard Analysis and Critical Control Point」と書きます。
日本語では、「危害要因分析と重要管理点」という意味です。
…と言われてもピンとこないですよね?
もっと簡単に言うと、
「食品を作るときに、危ないところを前もってチェックして、安全なものを作る方法」 です。
たとえば、給食のサラダに「洗い残し」があったらどうなるでしょう?
バイ菌が残っているかもしれません。
もし、それを食べた人が お腹をこわしたり、食中毒 になってしまったら…。
HACCPは、そういう危険をあらかじめ防ぐためのルールなんです。
なぜHACCPが必要なの?
食べ物の事故はとても怖いです。
たとえば、ハンバーグがちゃんと焼けていなくて、中にバイ菌が残っていたら…?
そのまま食べた人が お腹を壊したり、最悪の場合、命に関わる事故 が起こるかもしれません。
HACCPは、
・「どこでミスが起こりやすいか」
・「どうやったら安全になるか」
をしっかり考えて、作る途中できちんとチェックする方法です。
たとえば、ハンバーグ工場では、
「お肉の中までしっかり75℃で1分以上加熱する」
というルールを決めて、毎回ちゃんとできているか確認します。
それを守れば、安全な食品を届けられるというわけです。
日本ではHACCPが義務になっています!
実は、日本では 2021年6月 から、すべての食品関係の会社や工場でHACCPを導入することが法律で決められました。
これは、「食品衛生法」という法律が変わったからなんです。
つまり、
・パン屋さん
・レストラン
・スーパーのお惣菜コーナー
すべてのお店が、HACCPの仕組みを取り入れなくてはいけません。
でも、小さなお店や工場は、「簡略版HACCP」という簡単な方法でもOK!
詳しいやり方は、厚生労働省が手引書を出しています。
従来のやり方とHACCPの違いは?
昔は、「できあがった食品を最後に検査する」というやり方が多かったんです。
でも、それでは問題が起こったときにはもう手遅れ…。
お客さんの元に危ない商品が届いてしまうかもしれません。
HACCPは、「作っている途中でチェック!」 がポイント。
・手はちゃんと洗っている?
・包丁はキレイに消毒してある?
・肉はちゃんと火が通っている?
こんなチェックを毎回しながら作ります。
だから、HACCPは 「最初から安全をつくる」 やり方なんです。
HACCPの7つのルールと12の手順
HACCPは 7つの基本ルール と 12の手順 に沿って進めます。
具体例:カレーを作る工場
1.HACCP担当チームを作る
2.商品と作り方を説明(どんなカレー?どんな材料?)
3.作業の流れを図にする(材料を仕入れる→切る→煮る→冷ます→包装…)
4.危ないポイントを見つける(肉の加熱不足、異物混入など)
5.特に大事なチェックポイントを決める(お肉の加熱温度!)
6.具体的なルールを決める(75℃以上で1分以上加熱など)
7.温度計やタイマーでチェックして記録する
8.問題が起こったときの対応(再加熱・廃棄の判断)
9.記録をきちんと残す(後から見直せるように)
10.うまくできているか検証する
11.手順書にまとめて保存
12.スタッフ全員に教育と訓練を行う
HACCPを導入するメリットは?
食中毒のリスクがぐんと減る!
HACCPの一番のメリットは、食中毒をしっかり防げること です。
特に、次のような場面でHACCPはとても効果を発揮します。
① 細菌やウイルスの繁殖を防ぐ
食品は、温度や時間によって「細菌(ばい菌)」がどんどん増えてしまうことがあります。
たとえば、夏場にお弁当を作って放っておくと、
・黄色ブドウ球菌
・サルモネラ菌
・腸管出血性大腸菌(O157など)
などの危険な菌が増殖してしまい、食べた人が腹痛や下痢、ひどいときには命に関わることも…。
HACCPでは、「菌が増えにくい環境」を作るために、
・加熱は中心温度を75℃以上で1分以上守る
・冷却は90分以内に10℃以下に下げる
といったルールを決めて、必ず守ります。
これにより、細菌の繁殖をしっかり防ぐことができます。
② 異物混入を防ぐ
髪の毛、プラスチックのかけら、金属片などの異物が食品に混ざってしまうと、
・ケガの原因 になる
・信用を失ってしまう
などの大きな問題につながります。
HACCPでは、
・作業員は帽子やマスク、手袋を着用し、髪の毛や汗が落ちないようにする
・金属探知機を使って金属片の混入をチェック
・包丁やまな板を色分けして、アレルギーや交差汚染(菌が移ること)を防ぐ
こうした仕組みで、異物が入らないようにしています。
③ アレルギー事故を防ぐ
アレルギーがある人にとっては、たとえば 卵や乳製品、そば が入っている食品を間違って食べると、
・呼吸困難
・アナフィラキシーショック
といった命に関わる危険な状況になることがあります。
HACCPでは、
・アレルゲン(アレルギー物質)を含む原材料の保管場所を分ける
・アレルゲン対応の作業ラインを分けたり、清掃のルールを厳しくしたりして、混ざることを防ぎます。
・表示ミスを防ぐために、ラベル貼付作業のダブルチェックを行う
こうした取り組みで、アレルギー事故を未然に防ぐことができます。
④ ウイルスによる感染を防ぐ
冬場によく問題になる ノロウイルス は、ほんの少しのウイルスでも食べ物から感染し、
・激しい嘔吐や下痢
・集団感染
などが発生します。
HACCPでは、
・調理前の手洗いを正しい方法で徹底
・作業員が体調不良の場合は出勤停止にする
・調理器具の消毒をしっかり行う
などの対策をとります。
これによって、ノロウイルスの感染リスクを大幅に減らすことができます。
⑤ 二次汚染や交差汚染を防ぐ
「生の肉」を切った包丁で、そのまま「野菜」を切ると、肉にいた菌が野菜に移ってしまいます。
これを 二次汚染(交差汚染) といいます。
HACCPでは、
・包丁やまな板を用途別に色分け
・使用後はすぐに洗浄・消毒
などをルール化することで、汚染を防ぎます。
信頼されるお店や会社になれる!
「この工場や会社はHACCP認証を取得している」と分かれば、お客さまは「衛生管理がしっかりしていて安心」と感じ、信頼して商品を選んでくれます。
会社や工場が「HACCP認証を取得している」とウェブサイトや名刺に記載することで、衛生管理が徹底された信頼できる企業であることが伝わります。
取引先や顧客からの信用が高まり、ビジネスチャンスが広がることにも繋がります。
また、工場や事務所に認証証明書を掲示すれば、訪問したお客さまにも安心感を与えることができ、取引の決め手になるケースも増えています。
海外でも通用!
HACCPは世界基準。
国連のFAOやWHOもすすめていて、海外に食品を輸出したい場合も HACCPは必須 です。
HACCPは「ISO22000」「FSSC22000」といった国際認証にも組み込まれていて、特にFSSC22000は「グローバル食品安全イニシアチブ(GFSI)」にも認められた認証です。
HACCPをしないとどうなる?【罰則も!】
HACCPは法律で決まっているので、やらないと
・保健所から指導
・営業停止
・ひどい場合は 6か月以下の懲役か、50万円以下の罰金
さらに、食中毒などが起きるとニュースで報道されて、お店や会社の信用ガタ落ち… になってしまうことも。
HACCP認証ってなに?どう取るの?
HACCPをきちんと実施していると、外部の機関から 「HACCP認証」 をもらえます。
認証があると
・信頼がアップ
・ホームページやチラシに「認証取得済み!」と書ける
など、お店のアピールにもなります。
取得までにかかる期間は 8〜14ヶ月。
コストは規模によりますが、「JFS-B規格」は比較的短期間・低コストで導入できます。
HACCPに関する資格もある!
資格がなくてもHACCPはできますが、持っていると役立ちます。
たとえば…
・HACCP管理者
・HACCP普及指導員
・HACCPリーダー
取得できる機関はこちら
HACCP導入は低コストでも可能!
「HACCPってお金がかかりそう…」と思われがちですが、実は 無料の手引書 もたくさんあります。
小さなお店や工場なら「簡略版HACCP」でシンプルな記録とチェックをすれば大丈夫です。
HACCP導入はマニュアル作りから!
まずは「手順書」を作りましょう!
・写真やイラストを使って分かりやすく
・難しい言葉は使わない
・具体的に「どうやるか」を書く(加熱温度・時間など)
困ったときは、ISOコムのHACCP支援もあります!
HACCPはアポロ計画がルーツ!
実はHACCPは、アメリカのNASA(ナサ)が宇宙食の安全を守るために作った方法なんです!
宇宙飛行士が宇宙で お腹を壊したり、ケガをしたり したら大変!
だから、NASAは「絶対に安全な食品を作ろう!」と考えたのがHACCPの始まりです。
なんと、当時の目標は「100万食作って、不良品は1個あるかないか」 というレベル!
この厳しい管理が、今の食品工場でも生かされています。
HACCPはコストがかかる?…実は違います!
HACCPは「コストがかかりそう…」と思われがちですが、実際は コスト削減 になることが多いんです。
実際の事例
・HACCPを導入したら商品の鮮度が上がり、売上が伸びた!
・無駄やムラが減り、生産効率アップでコストも削減!
・賞味期限切れの廃棄も減って、利益率が上がった!
まとめ
HACCPは「食品を安全に届けるための仕組み」です。
むずかしく考えず、
・「危険を予測する」
・「大事なところをチェックする」
・「記録を残す」
…この3つが基本!
まずは、できることからHACCPを始めてみましょう!
ISOコムなら、HACCPをスムーズに導入するお手伝いができます。
HACCP取得のご依頼は今すぐお問合せフォームからご相談を!
ISOコム株式会社お問合せ窓口 0120-549-330
当社ISOコム株式会社は各種ISOの新規取得や更新の際のサポートを行っているコンサルタント会社です。
ベテランのコンサルタントが親切丁寧にサポートしますので、気になる方はぜひご連絡下さい。